介護をしていると、細切れで中途半端な時間が多くなります。
だから、就職した後はあまり読まなくなっていた小説を、隙間時間で読むようになりました。
いまさらになって、三国志なんかも読みました。
前半の主人公、劉備玄徳のどこに魅力があるのかが全く分からないのは、私の年齢のせい?性別のせい?
まあ、三国志は置いておくとして、
「ママ、いったいいつになったら死んでくれるの?」
水村美苗 母の遺産
どこかで自分も思っているかもしれないことを言い当てられたような気がして、購入した水村美苗さんの「母の遺産」
主人公の現在の人生や同世代だったころの母親の姿と若かりし頃の主人公の姿を行き来しつつ、既に亡き祖母の劇的な人生と母の生い立ちまでが交差しながら物語は進みます。
比較的経済的には恵まれている上に、翻訳という技術も持つ主人公。(翻訳家でもある著者 水村美苗さんの実体験も入っているのだそう)
介護も有料老人ホームで身体介護はプロに任せ、母の希望を満たしていくことに専念していく介護の形なのですが、主人公が消耗していく様子が読んでいて切ない。
(このあたり、今の私のように思考のスイッチを切ってしまって、おむつ交換とか食事の準備してる方が楽かもとも思いますが・・・実の親だとスイッチ切るのは難しいんでしょうね)
現在の母の姿に過去の母が重なり、母の姿に未来の自分の姿が重なり、考えることが2~3倍になってしまうことがとてもよく分かります。
母への思いの葛藤と夫の浮気、更年期症状の悪化などが重なりながら、主人公はこれまでの人間関係をもう一度捉えなおし、夫とも別れて、ひとりで自分の人生を歩み出します。
介護される人と介護する人の関係性の歴史が長いほど、距離感があいまいになりやすくて大変なんだなあ。。。と改めて思った一冊(上下あるので2冊ですかね)でした。
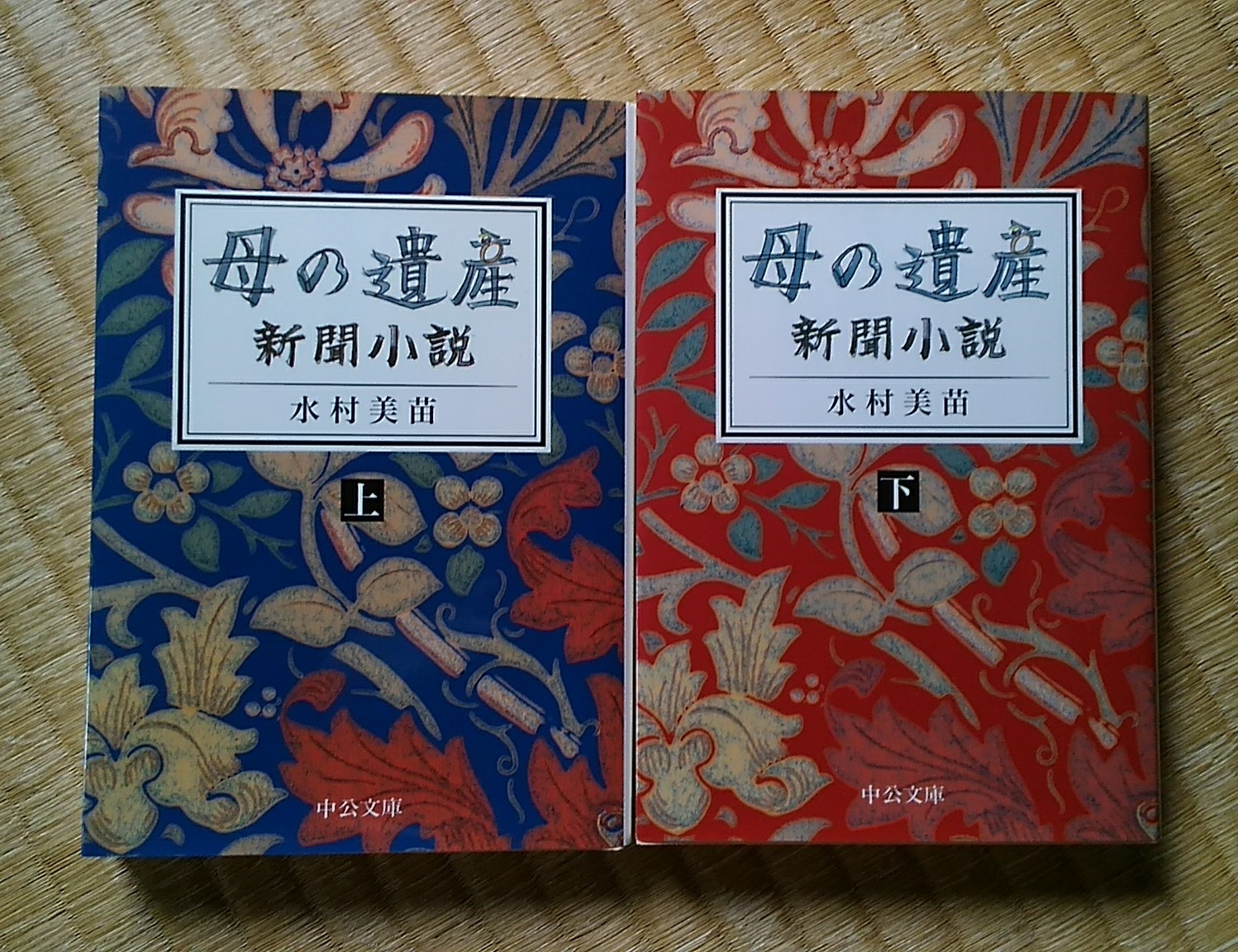



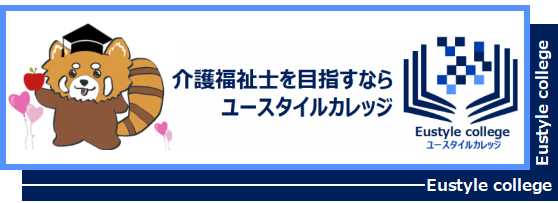


コメント